免疫力アップに必要な7つのチェックポイント
東京大学大学院農学生命科学研究科の上野川修一名誉教授の著書人生は運命ではなく「腸」が決めるによると、免疫力をアップするための7つのチェックポイントがあるそうです。
腸活「7つの習慣」
こちらの7つの項目は上野川修一名誉教授の7つのチェックポイントを腸活.jp風にアレンジした内容になっています。
- ビタミンA,C,D,Eなどが豊富な食品を積極的に食べること
- 食生活で不足しがちな亜鉛、セレンなどのミネラルを豊富に含んでいる食品を積極的に食べること
- 乳酸菌など、からだによい微生物を含んだ食品を積極的に食べること
- 自分の腸にいる有益な腸内細菌をもっと増やしてくれるような成分を含む食品を積極的に食べること
- 抗酸化成分を含んだ食品や水溶性食物繊維を積極的に食べること
- たんぱく質は積極的にとり、脂肪を取り過ぎないようにすること
- 食事は楽しみながらとるように心がけること
ひとつずつ説明していきます。
1 ビタミンA,C,D,Eなどが豊富な食品を積極的に食べること
免疫力をアップするために、抗酸化作用のあるビタミンを含んだ食事は欠かせません。

ビタミンAは腸管免疫系の維持に役立つ
ビタミンAは免疫学的に重要なビタミンで、免疫細胞を活性化して、細胞たちが充実した状態で働けるようにします。腸管免疫系の維持にビタミンAとその代謝産物であるレチノイン酸が重要な役割を果たしていることが明らかになっています。
ビタミンAは、レバー、うなぎなどの動物性食品、にんじん、ほうれんそうなどの野菜に含まれています。
ビタミンCは免疫細胞を活性化する
1gのビタミンCを20週間近く摂取すると、リンパ球などの免疫細胞が活性化されることがわかっています。ビタミンCの持つ抗酸化作用は、免疫細胞が活性酸素などによって機能低下するのを防ぐのです。
ビタミンCは赤ピーマン、ブロッコリー、芽キャベツなどの野菜類や、レモン、オレンジなどの果物に多く含まれています。
ビタミンDは自己免疫疾患を抑える
ビタミンDはもともと、骨の形成に重要な役割を果たしている栄養素として知られていましたが、それ以外に、自己免疫疾患を抑える働きがあることがわかっています。
自己免疫疾患とは、本来自分を攻撃しない免疫系が異常な状態となり、自分の組織器官を攻撃してしまう状態のことを言います。
ビタミンDはあん肝、さけ、にしん、さんま、干しきくらげなどに多く含まれます。
ビタミンEの2つの効用
ビタミンEの一つの機能に、ビタミンCと同じような抗酸化作用があります。
また、ビタミンEはプロスタグランジンE2(加齢で発生する免疫力を低下させる物質)の発生を防ぐ役割があります。
ビタミンEはアーモンドやピーナッツ、小麦胚芽などに多く含まれます。
複数の食品を組み合わせて食べたほうが効率よくビタミンを摂取できる
これらのビタミンは単独で摂取するよりも、多くの食品から摂取したほうが有効です。
たとえばビタミンCはビタミンEが壊れるのを防ぐなど、ビタミン同士で相互に助け合う働きがあるからです。
2 食生活で不足しがちな亜鉛、セレンなどのミネラルを豊富に含んでいる食品を積極的に食べること
ミネラル(金属)も免疫力アップにおいて重要な役割を持ちます。
からだが正常に働くためには、カルシウム、マグネシウム、鉄など、ミネラルが必要であることが科学的に証明されているのです。
日本人の一般的な傾向として、亜鉛、セレンが不足しがちです。
亜鉛・セレンは酵素の活性化に役立つ
亜鉛・セレンは酵素の活性化に役立ちます。酵素は活性酸素を除去する働きがあります。
したがって、食べ物から亜鉛やセレンを十分に補給していれば、からだの中の余分な活性酸素は分解されて、免疫機能は通常の状態を保つことができるのです。
亜鉛はカキ、豚レバー、豚肉赤身等に多く含まれます。
セレンは米(精白米)、卵、いわし、かれい、昆布、海草等に多く含まれます。
3 乳酸菌など、からだによい微生物を含んだ食品を積極的に食べること
人の腸内には、腸内環境を正常に保つ働きをする善玉菌が存在します。善玉菌には乳酸菌や納豆菌、酵母菌や麹菌などの様々な種類があります。
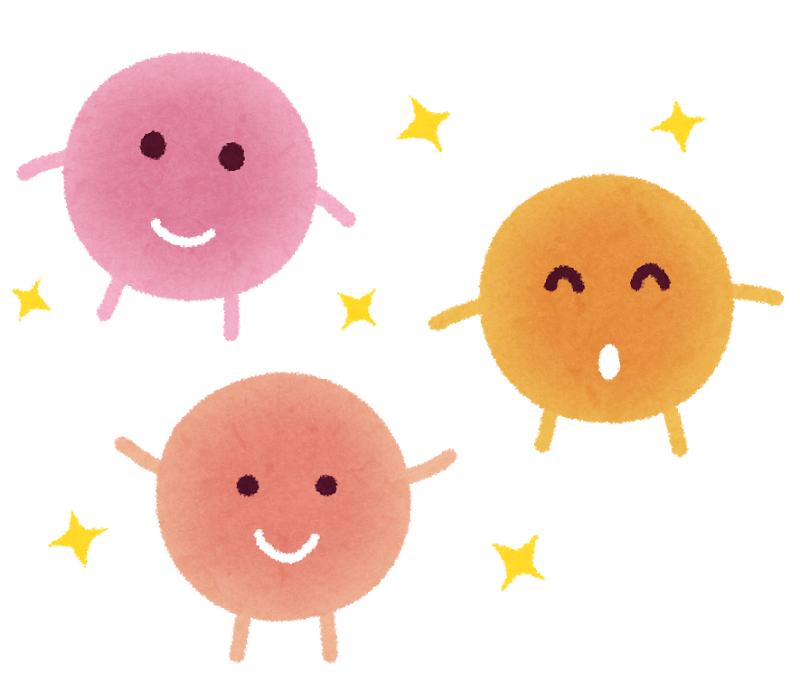
ビフィズス菌は善玉菌のメインプレーヤー
ビフィズス菌は成人の腸内における善玉菌の99%以上を占める菌です。ビフィズス菌は、母から子へ受け継がれることにより、人の腸に生まれながら存在する菌です。ビフィズス菌は腸内環境を整える、下痢や便秘を防ぐ、免疫力を高めるといった働きをします。酢酸を放出し、悪玉菌の生成を抑制することも可能です。
ビフィズス菌は年をとるごとに減っていく
腸内に最もビフィズス菌の量が多いのは生後1週間頃までで、その後、年齢と共に減少していきます。授乳期の赤ちゃんの腸内は、95%がビフィズス菌。生まれたての赤ちゃんの便色が鮮やかでニオイが少ないのは、ビフィズス菌によって健康な便が作られているためといわれています。ビフィズス菌は離乳が始まる頃から減少傾向となり、高齢期になると腸内のわずか1%ほどに減少します。
ビフィズス菌を増やそう!
ビフィズス菌の少ない腸には悪玉菌が増え、その結果、腸内にはアンモニアなどの腐敗産物が増え、腸内環境が悪化します。便秘や下痢、体臭や口臭、肌荒れ、病気を引き起こすこともあります。美容と健康をいつまでも維持するためには、積極的にビフィズス菌を摂取し、腸内のビフィズス菌量を増やすことが重要です。
4 自分の腸にいる有益な腸内細菌をもっと増やしてくれるような成分を含む食品を積極的に食べること
人間の腸内には100兆個以上、500種類以上、1キロ程度の腸内細菌が生息しています。
代表的な腸内細菌には以下のようなものがあります。
腸内細菌の種類
ビフィズス菌
バクテロイデス菌
ラクトバチルス菌
ユーバクテリウム
クロストリジウム
大腸菌
腸球菌
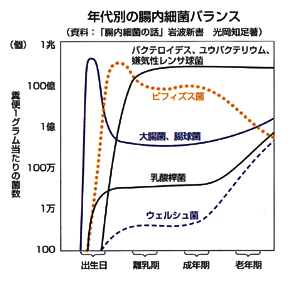
腸内細菌の集まりや、そのバランスのことを腸内フローラといいます。
腸内フローラを整える
さまざまな理由から腸内フローラが異常な状態になってしまうと、そこからさまざまな病気を引き起こす要因になります。
・アレルギー患者には有益菌であるラクトバチルス菌が少ない
・炎症性大腸炎という免疫異常の病気の患者にはビフィズス菌が少ない
・大腸がんの場合、腸内フローラの異常代謝が発症に関係している場合もある
・有益菌の数が相対的に少なくなると、腸内感染症にかかりやすくなる
反対に、腸内フローラを正常な状態に回復すれば、病気を予防することが可能になるということです。
プロバイオティクスとプレバイオティクス
プロバイオティクスとは
プロバイオティクスとは「有益な細菌を生きたまま取り出したもの」のことで以下の定義を持っています。
・腸内由来の(腸内にもともとあった)細菌であること
・からだによい影響を与えるもの
・食べたあと、胃などで消化吸収されることなく、生きた状態で腸まで届くもの
乳酸菌や納豆菌、ビフィズス菌などの有益な微生物のことをプロバイオティクスと言います。ヨーグルトは豊富なプロバイオティクスを含んだ食品です。
https://genieee.stores.jp/items/56f78bc2ef3377989a0063e5
プレバイオティクスとは
プレバイオティクスは、「腸内細菌の中の有益菌を増やすことができるもの」です。たとえば、ビフィズス菌のえさになるオリゴ糖があげられます。
オリゴ糖は善玉菌だけのえさになる
オリゴ糖のよいところは、有益菌(善玉菌)であるビフィズス菌やラクトバチルス菌のえさになり、さらに有害菌(悪玉菌)のえさにはならないということです。
オリゴ糖を含む食品
オリゴ糖を多く含む食品には以下のようなものがあります。
きな粉
ごぼう
たまねぎ
はちみつ
にんにく
ライ麦
豆腐
バナナ
腸内フローラを整えて、病原菌を撃退しよう!
腸内細菌が最良の状態にあると、コレラ菌などが体内に入り込んできても、割り込むことができません。腸内フローラが整っていると、感染症にかかりにくくなるということです。
アレルギーの人はラクトバチルス菌を増やそう
アレルギーは腸内のラクトバチルス菌が減っている状態の人に多いことがわかっています。オリゴ糖の含まれた食品を食べることによって、ラクトバチルス菌の数を増やせば、アレルギーは発症しにくくなると考えられるのです。
https://genieee.stores.jp/items/56dc33d63cd48233d8014b29
5 抗酸化成分を含んだ食品や水溶性食物繊維を積極的に食べること
冒頭で紹介したビタミンA,C,D,Eやミネラルを含む食品を、バランスよく摂ることで免疫力を上げることができます。
また、腸内細菌の栄養となる水溶性食物繊維を摂ることも重要なポイントです。
第六の栄養素、食物繊維
①タンパク質②脂質③糖質④ビタミン⑤ミネラルの5つの成分。第六の栄養素として注目されているのが「食物繊維」です。
食物繊維には「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」の2種類があります。
不溶性食物繊維と水溶性食物繊維
食物繊維には水に溶けない不溶性と、水に溶ける水溶性とがあります。不溶性の食物繊維は水分を吸って大きく膨らみ、便のかさを増やすことで腸のぜんどう運動を促してくれます。水溶性の食物繊維は水を含むとゲル状になり、便の水分を増やしてやわらかくしてくれるという働きがあります。
不溶性:水溶性
食材には不溶性と水溶性の食物繊維の両方が含まれていることがほとんどですが、そのバランスは食材により大きく異なります。たとえば、食物繊維の多い食材の代表ともいえるサツマイモは不溶性3:水溶性1。レタスは不溶性10:水溶性1と大きな開きがあります。
食品には不溶性食物繊維のほうが多く含まれる
不溶性食物繊維は自然と補うことができますが、水溶性食物繊維は、食べ物を選定しないと十分に取れないことが多いのです。
便秘をしている人が食物繊維を大量に摂取すると、ガスが溜まってお腹が張り、苦しくなることがあります。いわゆる「食物繊維を摂っているのに便秘気味」という現象は、不溶性の食物繊維が多い場合に起こりやすいのです。
不溶性2:水溶性1が理想のバランス
理想のバランスは不溶性2:水溶性1です。水溶性食物繊維を豊富に含む食材を多くとっていきましょう。
水溶性食物繊維を多く含む食材例
納豆
不溶性2:水溶性1と、理想的な食物繊維バランス。1パックで1日の必要量の1/7を摂取できます。
モロヘイヤ
栄養価が高い食材として知られています。ぬるぬるとした粘りにたっぷりと水溶性食物繊維が含まれます。
オクラ
ねばねばしているのが水溶性食物繊維のペクチン。生よりゆでたほうがペクチンの吸収がよくなります。
海藻
昆布やわかめ、もずくといった海藻類にはヘミセルロースという水溶性の食物繊維が豊富に含まれます。
なめこ
不溶性、水溶性ともに多く含んでいます。ぬめりに水溶性食物繊維が多いので洗わず使いましょう。
さといも
独特のぬめりがあることからもわかるように、イモ類のなかでも水溶性食物繊維が豊富です。
水溶性食物繊維は食べ物から摂取しづらいため、サプリメントで補うのも効果的です。
https://genieee.stores.jp/items/56d44f1bbfe24c8e2a0015f2
6 たんぱく質は積極的にとり、脂肪を取り過ぎないようにすること
たんぱく質で抵抗力がアップする
たんぱく質とは、アミノ酸が100個以上結合したものです。私たちの体は、生き物であるたんぱく質を食べて、アミノ酸に分解し、もう一度組み替えて細胞を作り、細胞を活性化させる酵素などを作っています。
たんぱく質が不足すると
たんぱく質が不足すると、細胞の働きが落ちてしまい、皮膚の細胞数が減少、免疫細胞の働きも落ちてしまいます。
脂肪のとりすぎに注意
食品成分のなかには、からだの抵抗力を抑えてしまうものがあります。代表格が脂質です。特定の脂肪酸に、免疫の働きを抑える作用が確認されています。脂肪酸は、細胞膜の重要な構成成分で、生命維持には欠くことのできないものですが、適切な量でないと、害を及ぼします。
体によい脂肪酸もある
以下のような脂肪酸は体によい影響を与えるので、積極的に摂っていきたいですね。
オリーブオイルやアボカドオイル
酸化しにくく、オレイン酸を多く含む
亜麻仁オイル、胡桃オイル、エゴマオイル
Ω-3(オメガ3)系脂肪酸を多く含む
ココナッツオイル
脂肪になりにくい中鎖脂肪酸を多く含む
7 食事は楽しみながらとるように心がけること
最後になりましたが、なんといっても、楽しみながら食事をすることが大切です。

腸内フローラを整えるという意識も大切ですが、食事管理をしすぎて、ご飯がおいしくなくなってしまっては元も子もありませんよね。
まとめ:腸活で美容と健康と長寿を手に入れる「7つの習慣」
もう一度7つの習慣をおさらいします。
- ビタミン
ビタミンA,C,D,Eなどが豊富な食品を積極的に食べること - ミネラル
食生活で不足しがちな亜鉛、セレンなどのミネラルを豊富に含んでいる食品を積極的に食べること - プロバイオティクス
乳酸菌など、からだによい微生物を含んだ食品を積極的に食べること - プレバイオティクス
自分の腸にいる有益な腸内細菌をもっと増やしてくれるような成分を含む食品を積極的に食べること - 水溶性食物繊維
抗酸化成分を含んだ食品や水溶性食物繊維を積極的に食べること - たんぱく質
たんぱく質は積極的にとり、脂肪を取り過ぎないようにすること - 楽しんで食べる
食事は楽しみながらとるように心がけること
すでに実践している習慣はありましたか?

正しい知識を持ち、好きなものをバランスよく食べることによって、身も心も満足していきましょう![]()
美腸エステ® GENIE(ジニー)&日本美腸協会
最新記事 by 美腸エステ® GENIE(ジニー)&日本美腸協会 (全て見る)
- 東京開催♪通うことでセルフケアを身につける新講座のご案内!! - 2018年1月17日
- 発酵玄米の魅力について♪ - 2018年1月15日
- 美腸プランナー1級勉強会❤️ - 2017年11月21日


